ひな薔薇綺譚の
物語
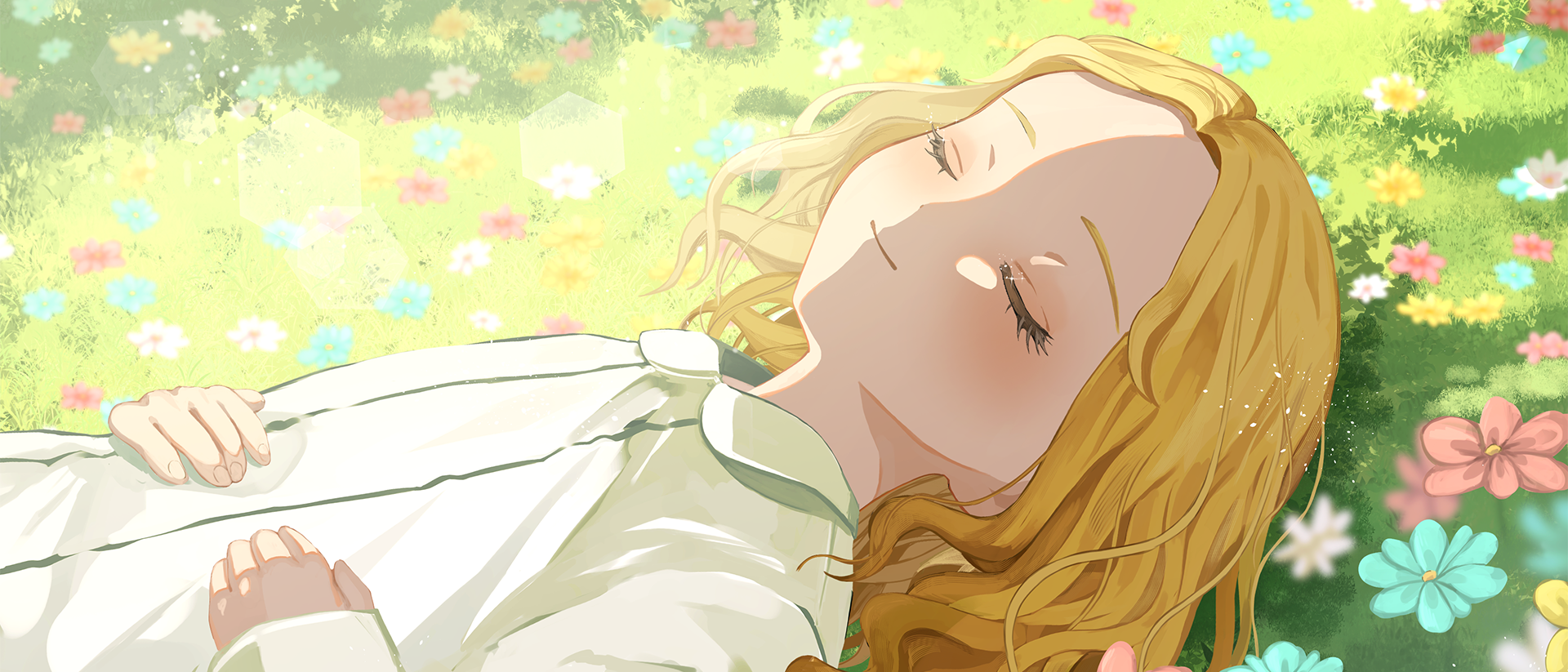
PROLOGUEプロローグ
- 気が付くと私はクマに抱かれていました。
- 温かいと思っていたのは、
- 彼女の毛皮のせいだったのです。
- 大きな躰と漆黒の瞳、
- 金色の太陽のように微笑みながら、
- 彼女は言いました。
- いっしょに暮らしましょう。
- 彼女はあまいハチミツの匂い、
- 私を待っていてくれる
- お日様みたいな
- たったひとつの大きな手。
- 目覚めた花みたいにほほえみながら、
- 心の魔法はまだはじまったばかりです。

第一章
ひな薔薇
第3話ルビーとシルヴィア

静けさが深く降り積もる森に、一本のミズナラの木が佇んでいる。ひな薔薇はそのたくましい大木を、親愛を込めて「ルビー」と呼んでいた。
はじめて出会った日、秋の光に晒されて赤く染まる葉を見て、まるで大きな宝石が森に宿っているようだと、ひな薔薇は思った。
あれから時がたち、再び森は秋を迎えている。
ルビーは燃え上がるように輝き、その大きく二手に分かれた幹のくぼみに、十二歳のひな薔薇が静かに腰を下ろしていた。
この森のことならたいていわかる。ひな薔薇はそんな気がしている。十歳の誕生日におばあさまから贈られたメッセージが、森で過ごす日々の道しるべになった。
ひな薔薇。森へ行きなさい。
森の中を走りなさい。飛び回りなさい。立ち止まって深呼吸しなさい。
空を見上げ、花を見つけ、小川のせせらぎに耳を澄ましなさい。
蟻を見つめなさい。蝶々といっしょに優雅に踊りなさい。
心地のいいところまで、あなたの心の器を埋めなさい。
あなたが何者であるか、あなた自身が決めなさい。
あなたのルーツはこの夢の森にある。
あなたも知らない力が、あなたの中に眠っているの。
♢♢♢♢♢♢
その日の森は、ひそやかな気配が満ちていた。風は静かに枝を揺らし、ルビーの葉は遠くの水音のように微かにささやいている。それは言葉にならない祈りのように、森の奥へ、あるいは空へ向かって、静かに放たれていた。
――ひな薔薇はルビーの姿がとても好きだ。広がる枝は翼のようで、いつかルビーが空を飛ぶと信じている。ひな薔薇はルビーのそばにいるだけでなんだか幸せな気持ちになる。
深呼吸をすると、躰中がおいしい空気でいっぱいになって、いつのまにか笑っている。お日様を浴びてルビーの葉がきらきら光っているときも、雨に濡れているときも、ただそばにいるだけで、いつでもルビーは頼もしい存在だった。
「やあ。ひな薔薇」
老キツネのシルヴィアがやってきて、ひな薔薇を呼んだ。
「シルヴィア、久しぶりね」
「ああ。森は真っ赤だし、黄色だし。どうだい? いっしょに歩かないかい?」
ひな薔薇はルビーから飛び降りた。
「行こう」
「今日はやけにノリがいいね」
「先に言っておくけど、今日はおやつを持っていないからね」
「あたしがあんたのおやつをポケットから出させて、食べちゃったことを言っているのかい? ほんの数回のことじゃないか」
「最近はいつもシルヴィアの分も、ポケットに入れて持ち歩くようにしているからねー」
「ああ。ありがたいね。さあ、行くよ」
秋の森はほろほろと美しい。黄金や深紅の木々、落ち葉の絨毯を踏みしめながら二人は歩いた。小川は冷たい秋風に吹かれながら、透きとおって流れていく。木々の間を縫うように歩くと、エゾリンドウの群れがひっそりと咲いているのを見つける。
二人は黒の森に辿り着いた。背の高いエゾマツが天に向かってそびえ立ち、空はほとんど見えない。辺りはじめじめとして、青々とした苔が瞬いている。ここでは二人はちっぽけな点になる。シルヴィアの毛がキラキラと輝き、微かな光は星みたいだ。
「ねえ、どこに行くの?」
シルヴィアはにやりと笑った。
「見事な夕焼けを見たいと思わないかい?」
「見たい」
ひな薔薇は前のめりになって言った。
「ピンク色の空、すごく綺麗だもの」
シルヴィアは耳まで口角を上げて笑った。
「特別な場所に連れていってやるよ」
「シルヴィア、今日はやけに優しいなぁ」
「あたしはいつでも優しいはずさ。あんたにだけはね」
「シルヴィアって、私のおばあさまに似てるんだ。ちょっといじわるで、でも優しくて、不思議なところが」
「あんたのとこの変わり者のばあさんといっしょにされちゃ、たまらないよ」
「おばあさまはシルヴィアと似ているって言ったら、すごく喜んでいたな」
「やっぱり変わり者だよ」
シルヴィアはあきれた様子で首を横に振った。
「シルヴィアのおやつを用意してくれるのも、おばあさまなんだけどな」
シルヴィアは肩をすくめてにやりと笑った。
♢♢♢♢♢♢
黒の森を抜けると、ようやく二人は小高い丘に辿り着いた。薄い雲がゆったりと空を漂い、ピンク色に染まっている。遠くで鳥たちのさえずる声が聞こえる。時間が経つにつれて、空はもっと深い色に変わっていった。
ピンクから紫へ、そしてゆっくり夕闇が降りてくる。ひな薔薇は夕暮れの風に吹かれながら、言葉もなくその風景を眺めている。シルヴィアは満足そうに瞬きをした。
「ひな薔薇。あんたの顔を見ればわかる。喜んでくれて、うれしいよ」
「ねえ、涙ってこんなときにも流れるものなのかな」
「あんたは泣かない子どもだからね」
「うん。おばあさまいわく、私は涙を持たない女の子なんだって」
「ばあさんの話は眉唾ものだがね。ひな薔薇、この森では人間だって、涙なんて必要ないのさ。森の動物と変わりゃしないんだから。でも、あんたが泣きたいって思うほど綺麗なものを、もっと見せてやりたかったね」
「まるでもう会えないみたいな言い方ね」
「あたしはもう、あんたとはさよならさ。冬がきて、あんたの首が寒くたって、温めてあげられる毛皮もないんだ。もうシワシワだからね」
「シルヴィアの毛皮、大好き。キラキラしてて」
「黒の森の中では、あたしの毛皮も少しは役に立ったかね」
「うん。あなたの毛皮は、いつだって私の星だった」
「ありがとうよ。あたしはね、もうすぐ星になるんだ。つまり、死ぬってことさ。ひな薔薇、あんたにお願いがある。あたしは女の子の腕の中で死にたいって、ずっと夢見ていた。つまり、あんたの腕の中でね。今すぐ、あたしを抱いてくれるかい?」
ひな薔薇はシルヴィアをその腕の中に抱いた。シルヴィアの躰は暖かかった。でも、その毛皮は硬く閉ざされ、そのほとんどが骨と皮だった。
「シルヴィア、本当に痩せっぽちね」
「ああ。ここまで生きてこられたのが奇跡さ。あたしが死んだら星になって、きっとあんたを見ているよ。ひな薔薇」
「だったら。夜空を見上げれば、あなたに会えるのね」
「そういうことだね。それにしても、女の子の腕の中は暖かいねえ」
二人はそれきり、何も話さず空を眺めた。そのうちシルヴィアは、ひな薔薇の腕の中で静かに目を閉じた。シルヴィアの呼吸が浅くなり、穏やかな風のように弱くなっていく。
ときどき聴こえた鳥の鳴き声も止んで、丘の上はしんとなって、シルヴィアの息がゆっくりと途絶えた。ひな薔薇は微笑むようなその死に顔にそっと頬を寄せた。丘にはすでに夜が訪れ、空には星が瞬いている。
「シルヴィア、ルビーのところに帰ろうね」
ひな薔薇はシルヴィアを抱いたまま、元来た道を歩いた。空の高いところに満月が昇り、二人の道を照らした。丘を下り、黒の森を抜け、見慣れた風景の場所までやってくると、ひな薔薇にかなしみが降りてくる。
ひな薔薇は辿り着いたルビーの元に、冷たく、硬くなったシルヴィアの躰をそっと降ろした。
「ルビー。シルヴィアが死んだの。あなたのそばにいさせてあげて」
ルビーは何も言わない。いつも通り静かで、いつも通り堂々としている。ひな薔薇はシルヴィアの隣に横たわった。ひな薔薇の目の奥には、シルヴィアの毛皮に宿る小さな星が光っていた。
森の深い息づかいが、静かにひな薔薇を包んでいた。祈るように、ひな薔薇はそっと目を閉じた。
♢♢♢♢♢♢
おばあさまがやってきて、眠っているひな薔薇の頬に触れた。おばあさまはひな薔薇の隣に横たわるシルヴィアを見つけて、そっと手を合わせる。それからひな薔薇を抱きかかえた。
おばあさまはルビーを見上げながらしばらくの間立ち尽くし、自分の過去を追いかけた。楽しことばかりじゃなかったし、いいことばかりでもなかった。でも、私には愛する人がいた。そして今、ひな薔薇がそばにいる。
ミズナラの木よ。あなたのように、春の新緑、夏の陰、秋の彩りを、ずっとあの子に与え続けることができるのなら。私はずっとひな薔薇に寄り添うことができるのに。
おばあさまは叶わない願いを胸に抱きながら、いつか訪れる最期の日に思いを馳せる。
私のひな薔薇。
私の余白の人生に寄り添った女の子。
私の愛するたった一人の、永遠の女の子が幸せでありますように。







