ひな薔薇綺譚の
物語
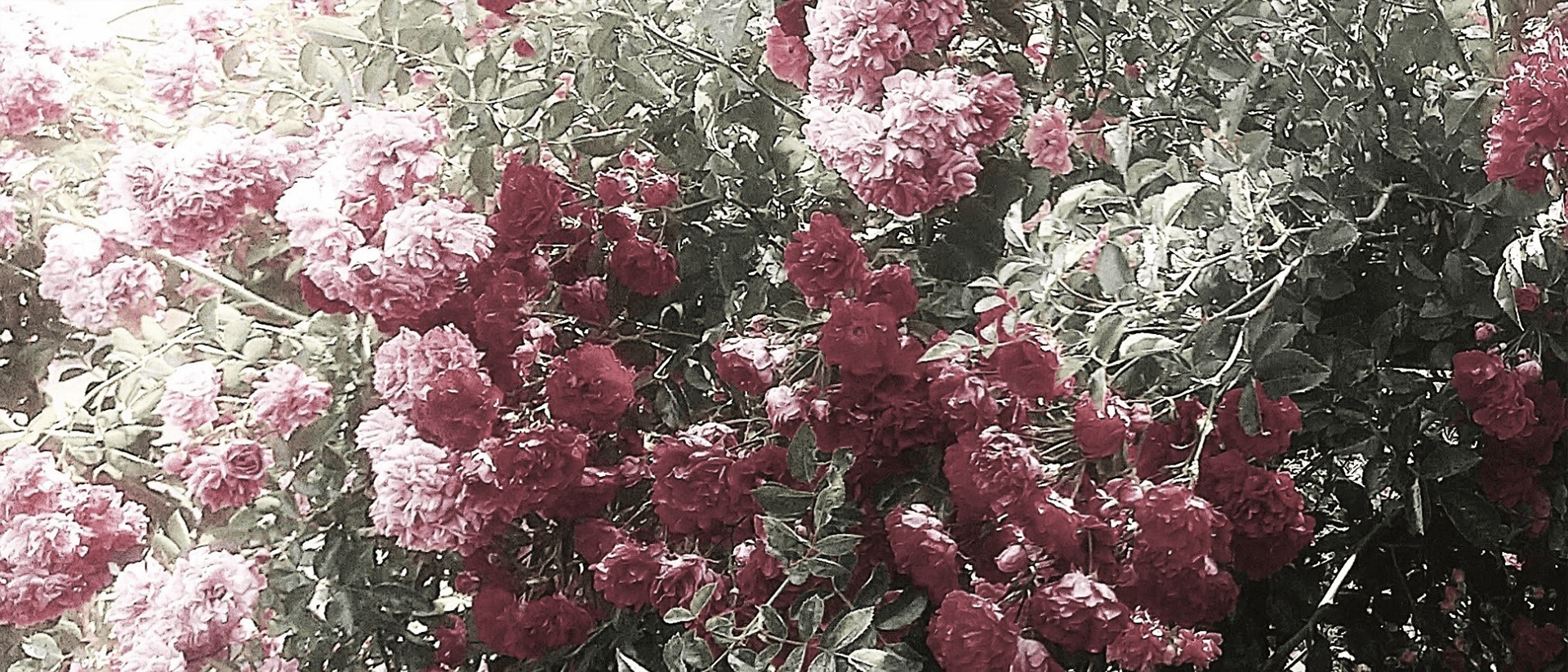
PROLOGUEプロローグ
- 気が付くと私はクマに抱かれていました。
- 温かいと思っていたのは、
- 彼女の毛皮のせいだったのです。
- 大きな躰と漆黒の瞳、
- 金色の太陽のように微笑みながら、
- 彼女は言いました。
- いっしょに暮らしましょう。
- 彼女はあまいハチミツの匂い、
- 私を待っていてくれる
- お日様みたいな
- たったひとつの大きな手。
- 目覚めた花みたいにほほえみながら、
- 心の魔法はまだはじまったばかりです。

第一章
ひな薔薇
第1話夢の森
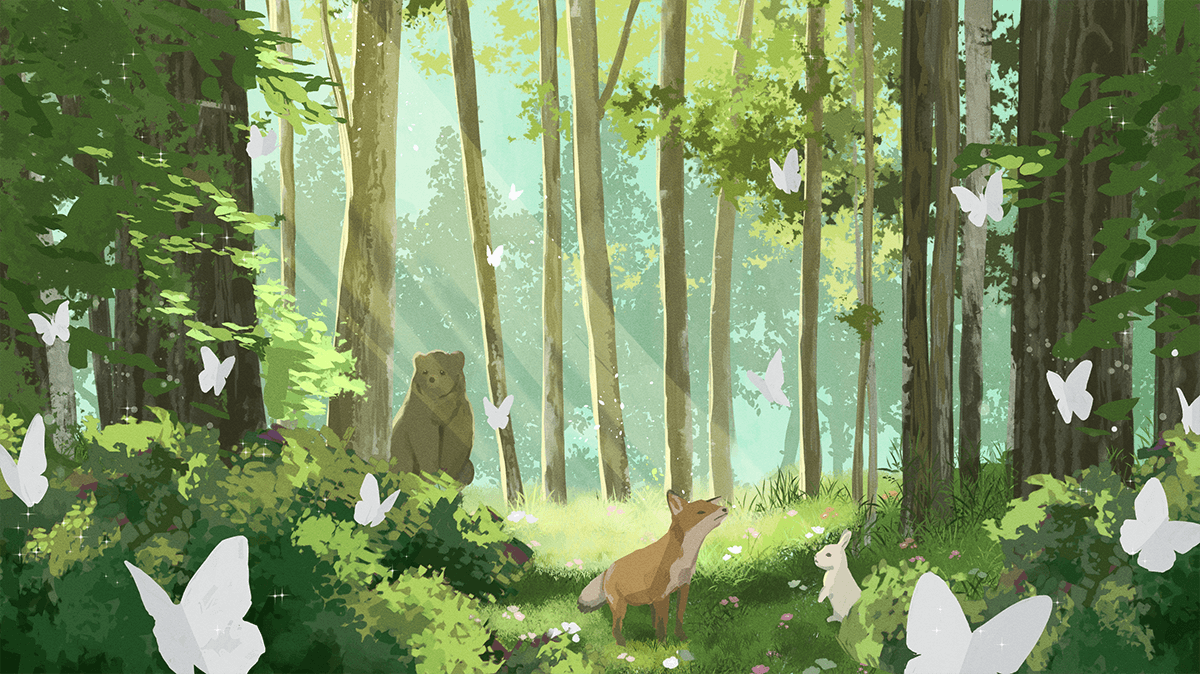
風が吹くと、シラカバの木々がいっせいに揺れる。
水色の空がずっと遠くの方にあって、
薄い雲が流れていく。
風がひな薔薇の頬をくすぐる。
ひな薔薇の住む夏の森は青空と緑でできている。もちろん、雨の日だってある。旅の途中の雨が、静かに或いは情熱的に森を通りすぎるとき、ひな薔薇の胸はいつだって高鳴る。
鮮やかな緑は潤みながら風に揺れ、空気は明るく澄み渡る。目を閉じていても緑を感じることができるし、空さえ手に取るようにそこにある。それはまるで夢の果てのようだ。
たとえばここを夢の森と呼ぼう。
ひな薔薇とおばあさまが二人で暮らす古い家は、枯れた木々を彷彿とさせる。まるで辺りの木々に溶け込むかのように、小さな家は佇んでいる。家の前には緑の小道、それを挟んで片方に野菜畑があり、もう片方には花畑がある。緑々と、きらめく恵みにあふれている。
家の窓からは、森が見え、庭が見え、花が見え、道が見える。
窓からそれらを眺めると、そのすべてがとても遠いもののように感じる。手を伸ばせばすぐそこにあり、すぐにでも外に出ていって、それが何であろうと触れることだってできるというのに。にもかかわらず、二つの世界の間には、独特の遠近感があり、透きとおった一枚の幕が降ろされている。この窓は薄緑の瓶底のようにも思える。
ひな薔薇とおばあさまは、今日も庭の畑で野菜を収穫する。
「ひな薔薇。トマトを捥いでちょうだい。キュウリも大きくなり過ぎるから、収穫しなくちゃね」
おばあさまはハーブを摘んでいる。そばで蝶々が飛んでいくのを眺めていたひな薔薇は、はーい、と返事をして立ち上がった。ひな薔薇は立ち止まったまま、風の音に耳を澄ました。ざわざわざわ。るるるー。ざわざわざわ。るるるー。蝶々は目の前を横切った後、風に乗ってどこかへ行ってしまった。
ひな薔薇は物心がつく前に、この家にもらわれてきたらしい。彼女は何も覚えていない。去年の夏、同じように庭で畑仕事をしているとき、おばあさまはひな薔薇を膝の上に抱いて言った。
「あなたをもらってよかった」
おばあさまの顔に陽の光が差し、日焼けした肌が黒々と輝いて、とても綺麗だ、とひな薔薇は思った。
「おばあさま。私、おばあさまのところへもらわれてよかった」
五歳のひな薔薇は、にこにこしながらそう答えた。その頃のひな薔薇にとって、おばあさまの存在が心の半分を占めていて、残りの半分は空白だった。
でも、六歳のひな薔薇は少し違った。おばあさまの他に、今では風と木と蝶がひな薔薇の心に棲みついている。それらはひな薔薇の一部分になって、彼女の中に存在する、とても親しいものたちだ。
棲みついていながらそれらについて、ひな薔薇は何も知らない。木々はいつもそこにあるけれど、どこからきたのだろう。風はどこから吹いてくるのだろう。蝶々はどこからきて、どこに行くのだろう。
子どもらしく浮かびあがるそんな不思議が、消えては浮かび、浮かんでは消えてを繰り返す。ひな薔薇はそれを秘密と呼んで、夢の糸として紡ぐ。けれど今、ひな薔薇に新しい秘密が生まれた。
私、どこからきたんだろう。
それは最初のうち、突然生まれた小さな秘密に過ぎなかった。でも、ほんの短い間にそれは大地を揺する大きな波になり、切実な夢想に変わった。ひな薔薇は急いでおばあさまに駆け寄った。
「おばあさま。私はどこからこの家にきたの?」
おばあさまはハーブを摘む手を止めて、ひな薔薇を見つめた。おばあさまはとても冷静だった。
「どうしても知りたい?」
ひな薔薇はこくりと頷いた。おばあさまは諦めたように首を横に振った。
「あなたも、もう六歳だもの。無理もないわ。ひな薔薇、よくお聞き」
おばあさまは声をひそめて言った。
「森の奥のキツネの巣の中で、小さなあなたはひとりで眠っていたの。あなたを見つけたとき、私の女の子だと思った。そのとき私はすでにお母さんと呼ばれる年齢ではなかったけれど、どうしてもあなたが欲しかった。私は小さなあなたを連れ帰って、大切に育てることにしたの。いわば、私は森からあなたをもらった」
「私は棄てられた子どもなの?」
「それはどうかしら。きっと、どこかの家で見かけたひな薔薇を、キツネが巣に連れて帰ったんじゃないかしら。あなたがあんまりかわいかったから」
「キツネがどうやって人の家に入るの?」
「簡単よ。キツネは化けることができるんだから。お母さんの姿になって家に入り込み、あなたをさらったの。でも、きっとキツネはあなたを育てるのは難しいと諦めて、穴を後にしたのかもしれない」
ひな薔薇は恐くなっておばあさまに抱きついた。おばあさまはひな薔薇の背中を優しく撫でながら、嘘よ、と呟いた。
「ひな薔薇、ちょっとしたおとぎ話よ。ほら。トマトを捥いでおいで。お昼はトマトスパゲッティーにしましょう」
おばあさまは微笑んだ。ひな薔薇はおばあさまの元を離れ、トマトを捥ぎとった。真っ赤なトマトを噛むと、口からあまい汁が滴った。どうして? ひな薔薇はおばあさまの嘘に納得がいかなくて、再びその元へ駆け寄った。
「おばあさま、どうして嘘をついたの? 私、とても恐かった」
「ひな薔薇。人生は嘘と本当が混じって、ひとつの本当になるの。ひな薔薇も私も、おとぎ話の中で生きているのよ」
おばあさまは、ひな薔薇の口元を指で拭いながら言った。
「ひな薔薇には風の歌が聴こえるでしょう」
ひな薔薇は耳を澄ました。ひな薔薇には、どんな微かな風の歌も聴こえる。それは皮膚を伝って、やがて心臓まで潜りこむ。あなたの心臓が鳴り続けるのは、風の歌の恵みなのよ。おばあさまはひな薔薇を抱きしめながらそう言った。
野菜の収穫を終えると、ひな薔薇とおばあさまは家へと戻る。家に入り、ふっと空気が暗くなる瞬間、守られているような気がして二人とも安堵する。台所のテーブルは、あっという間に収穫した野菜たちでいっぱいになった。
さっそくおばあさまは、庭で収穫したトマトとバジルでスパゲッティーを拵えはじめた。
「ひな薔薇、キュウリのサラダを作ってね」
「はーい」
ひな薔薇はキュウリを切って、そのうえにミントの葉をちぎって散らし、おばあさま特製のドレッシングを垂らす。小さなボウルの中で、キュウリが輝いている。野菜たちは愛情と情熱に応えて、いつでもおいしい料理に変身する。台所はいい香りでいっぱいだ。
台所はこの家の魂だ。
窓から柔らかな陽差しが差し込み、床には風に揺れる葉影が映っている。テーブルに料理が並び、椅子に座ると、まずは二人で冷たいお茶をごくごく飲む。喉が潤った後は、完璧な昼食の時間だ。真っ赤なトマトスパゲッティーと真っ青なキュウリのサラダ。二人ともじつによく食べる。
二人で食事を平らげると、おばあさまは摘みたてのハーブで温かいお茶を淹れる。
「さあ。お茶を飲んだら、仕事の時間よ」
「はーい」
ひな薔薇はにこりと笑って返事をした。
おばあさまは裁縫を生業としている。
「あなたには親がいないのだから、裁縫を覚えなさい。そうすれば、私がいなくなった後も、きっと生きていけるのだから」
おばあさまはそう言って、ひな薔薇に裁縫を教えてくれる。
ひな薔薇は人形もおもちゃも持たない。そのかわりおばあさまは、色とりどりの布や細工ボタン、きらきらしたビーズなんかを惜しみなく与えてくれる。ひな薔薇はそれらを使って、好きなものをこしらえる。
まだ小さなひな薔薇が、針で指を刺してしまうことも、ハサミで手を切ってしまうことも、おばあさまは静かに見守ってくれる。もしもひな薔薇が傷ついてしまったときは、手当をしてくれる。
台所の隣にある裁縫部屋はこの家の心臓だ。
棚に並べられた色とりどりの布地、その隣には年代物のおばあさまのミシンが佇んでいる。部屋の真ん中には大きな作業机があり、そこにパターン、裁縫箱、針山がスタンバイしている。一見雑多に見えるこの部屋は、おばあさまの法則によって、実はすっかり整頓されている。
ひな薔薇は椅子に掛けて、ハンカチにマーガレットの刺繍をはじめた。白い布に少しずつ小さな花が生まれていく。
おばあさまは生地にパターンを当て、裁断していく。お得意さまから、秋のワンピースの注文が届いているのだ。裁断を済ませると生地にまち針を打ち、仮縫いをはじめる。もう何度も作っている定番のワンピースだからこそ、おばあさまは手を抜かない。
おばあさまはひな薔薇に耳打ちする。私には裁縫の神様がついているの。だからいつだって、完璧なお洋服を作ることができるのよ。確かに裁縫をしているときのおばあさまは特別だ、とひな薔薇は思う。
ひな薔薇にとっておばあさまの細い指は神様よりも魔法みたいで、仕事をしているときの顔が好きで、ときどきその横顔をじっと見つめてしまう。
「っつ…」
ひな薔薇はおばあさまに見惚れて人差し指に針を刺してしまった。指先から、ぷっくりと血液が盛り上がっている。
「ひな薔薇、そのままよ」
おばあさまは薬箱を取りにいった。指先の血を吸ってしまいたい。ひな薔薇は衝動に駆られながら、血の玉を見つめる。でも、結局そうすることもしないで、黙っておばあさまを待つ。おばあさまは薬箱を抱えて戻ってきて、大事そうにひな薔薇の指先をつまんだ。おばあさまはひな薔薇の血液をうっとりと見つめた後、ガーゼでそれをきれいに拭い、絆創膏を貼ってくれた。
「ひな薔薇の血は本当に綺麗ね」
ひな薔薇はおばあさまを見つめた。
「ブルーがかっていて、それでいて鮮やか。しかも鮮やかなのは赤じゃない。ブルーの方。美しい紺碧があなたの中を流れている。あなたの生命の流れを示唆している」
おばあさまの言葉はときどき恐い。おばあさまの言葉は確かな力を持っているから、簡単にひな薔薇の琴線に触れてしまう。混沌とした自分の過去が、思いがけず開きそうな気がして、ひな薔薇は蒼ざめた。
「ひな薔薇、おとぎ話よ。ひな薔薇の血に、ブルーが混じっているなんて素敵でしょう」
「おばあさまは本当にそう思うの?」
おばあさまは頷いた。
「もちろん。ひな薔薇、ブルーはこの世でもっとも美しい色のひとつよ」
おばあさまは傷ついたひな薔薇の手を、そっと握った。
「さあ。仕事を片づけてしまいましょう。その後は、ひな薔薇の好きな遊びをしよう。何でもOKよ」
「何でも? だったら川に行きたい」
「昨日作ったアップルパイを持っていこうか。レモネードも忘れずにね」
「おとといのクッキーも」
「そうね。好きなおやつをたくさん持って、川へ行こう」
そう言っておばあさまは仮縫いの続きをはじめた。すぐそばに、おばあさまの描いたお洋服のデザイン画が広げられている。胸にタックが入ったへちま襟のワンピースは、風が吹くとふんわりと膨らむだろう。ワンピースが形になっていくのを見ていると、ひな薔薇はどうしてもそれが欲しいと思った。夢を見て、憧れて、瞳をきらきらさせながら、おばあさまの指先を見つめた。
「お客さまのワンピースが縫い上がったら、ひな薔薇にもっとかわいい洋服を作ってあげる」
おばあさまはひな薔薇の手が完全に止まっているのに気付いて、そう言った。ひな薔薇は首を横に振った。
「おばあさま。それがいい。ふんわりしている、それがいいの」
「ひな薔薇、わかったわ。同じものをあなたにも作ってあげましょうね。さあ、あと三時間と千秒仕事をしたら、川へ行くわよ」
千秒はおばあさまの好きな単位だ。長くもない短くもない時間に意味があるの。たとえば千秒の間に小さな夢を叶えることだってできる。二千秒だったらどうかしら? 千秒が二つもあるのよ。つまり、どこか好き場所へ行って帰ってくることだってできるし、好きな人に会いにいくことだってできる。夢のようじゃない?
おばあさまはずるをして、千秒の前にたくさんの時間をつけることがあるけれど、それでもひな薔薇はいつだって心躍らせる。
ひな薔薇は待ちきれない気持ちで三時間と千秒後を思った。
仕事を終えて、ひな薔薇とおばあさまは夏の夕暮れの小川に向かった。川に着くと、二人で石を積んでダムを作り、魚の家をこしらえて遊んだ。ひな薔薇は葉っぱの舟を川に浮かべて、いくつもの舟出を見送りながら手を振った。
それから二人は小川のほとりに並んで座った。冷たい水の流れが足の裏を撫でていく。木々の間を抜ける風は涼しく、水面に薄紅の夕影がゆらゆら揺れている。おばあさまが用意したアップルパイとレモネードを二人で食べる。
「おばあさま。おいしいね」
おばあさまは優しく微笑んだ。
「こうやって川岸にひな薔薇と座っていると、誰かを待っているような気持ちになる。二人で迷子になってしまったような」
「こういう迷子だったら恐くない。だって、おばあさまといっしょだもの」
「そうね。ひな薔薇とずっといっしょにいられるといい」
おばあさまは川に映る夕暮れを見つめている。ひな薔薇は思う。おばあさまは、本当は独りきり誰かを待っているのかもしれない。おばあさまはときどき、種のないきゅうりみたいに弱くて青い。風が吹くと、すぐに折れてしまいそうなくらい独りきりだ。
「暗くなってきたわね。そろそろ帰ろうか」
おばあさまは立ち上がって、空を見上げた。空の高い場所にいちばん星が見えた。おばあさまは微笑みながら、星に向かって手を振った。そして、静かに願いごとを呟いた。
「あの日の幸せが、ひな薔薇にも訪れますように」
星の光はそっとふくらみ、それからゆっくりと瞬いた。すぐそばを雫のような流れ星がかすめとおると、おばあさまの顔が輝いた。願いは叶う。おばあさまはそう言うと、夕闇の中、ひな薔薇の手を握りしめて歩きだした。
夜の帳が静かに下りると、ひな薔薇とおばあさまは二人それぞれ小さな部屋で眠った。ひとつの部屋の真ん中に、おばあさまが拵えた麻のカーテンを吊るした二つの部屋。
寝室はこの家のオアシスだ。
ひな薔薇はベッドに横になる。ひな薔薇の心に浮かんでは消えていくもの。消えては浮かびあがるもの。ひな薔薇は微笑む。
ひな薔薇は枕に顔をうずめ、毛布に包まれて、ベッドに躰を預ける。躰がふわりと軽やかに解けていく。
一日の終わりは満ち足りている。今日も楽しかったな。夏の夜、窓を開けて眠ると、部屋は緑の匂いに包まれる。しんとした森の真上で、星々が天に瞬く。窓は薄緑の気体になって宇宙に浮かぶ。見降ろせば夢の森が広がっている。
