ひな薔薇綺譚の
物語
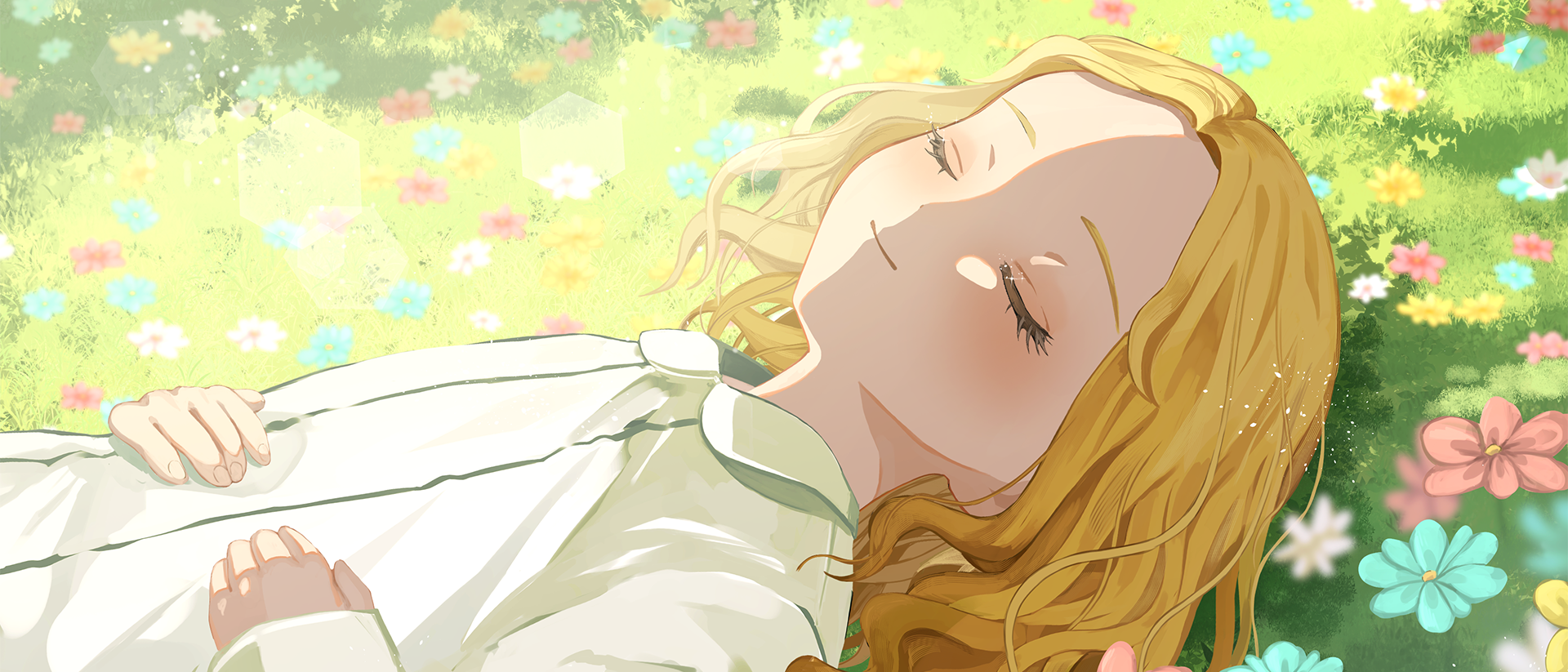
PROLOGUEプロローグ
- 気が付くと私はクマに抱かれていました。
- 温かいと思っていたのは、
- 彼女の毛皮のせいだったのです。
- 大きな躰と漆黒の瞳、
- 金色の太陽のように微笑みながら、
- 彼女は言いました。
- いっしょに暮らしましょう。
- 彼女はあまいハチミツの匂い、
- 私を待っていてくれる
- お日様みたいな
- たったひとつの大きな手。
- 目覚めた花みたいにほほえみながら、
- 心の魔法はまだはじまったばかりです。

第一章
リバティハウス * 札幌 *
第1話リバティハウス

リバティハウスは大通公園の外れに建つ、石造りの古い邸である。
赤い屋根とグレーの壁、無限の窓。
その美しさゆえにまるで架空のもののように語られる。
けれど、確かにリバティハウスはここにあって、人間化した動物たちが暮らしている。
動物たちは、森の女王である花音という道標に導かれて、この夢の邸で生きていた。
♢
キタキツネの水緑は、二階の窓からひな薔薇が歩いてくるのを確認した。
新たに花音が選んだ相棒を、自分なりのやり方で祝福したい、と待ち構えていたのだ。
大きなボストンバッグを持ったひな薔薇は、シンプルな生成り色のワンピースをまとっている。繊細に見えるけれど力強い、張りのある丈夫な木綿の充実感だ。
水緑はもうすぐひな薔薇の部屋になる場所から、声を掛ける。風のような呪文のような声が、ひな薔薇の名前を呼んだ。
ひな薔薇は微かに反応して、左右に首を揺らした。それから耳を澄ましているみたいに、じっと動かなくなった。声の主を探しているのかもしれない。水緑はほくそ笑む。
「ひな薔薇さま、執事のメイでございます」
リバティハウスの荘厳なドアを開けて、ヒツジの執事であるメイがやってきた。
「お荷物を」
「ううん。重いから」
「お任せを。おや!……これは」
メイはよろめきながら小さく叫んだ。
「これは到底常人が、ましてや女の子が持って耐えられる重さのものではございませぬ」
ほぉ…と水緑は声をあげる。ふうん。怪力ってことね。
「このような重い荷物をお一人で持ってこられた。わたしはそれについて、少しばかり感激しております」
「宝物を詰めこんできたの」
「それは素敵ですね」
メイに導かれてひな薔薇はリバティハウスに足を踏み入れた。
ひな薔薇の一挙手一投足を見逃さないために、水緑はすでに移動して、リビングルームの天井に張りついている。
光が降り注ぐエントランス、それから豪奢なリビングルーム。
クイーンアン脚が施されたソファー、たっぷりとしたドレープのカーテン、百万本とも思われる薔薇の花がそこいら中に飾られている。
「ここはお城?」
ひな薔薇の頬が紅色に変わった。
「ただいま、花音さまを呼んでまいります。しばしお待ちを」
メイがそう言って立ち去ったのを確かめると、水緑は天井から灰色の光を送った。
ひな薔薇の頬に射した紅を、消し去ろうとたくらんだのだ。強い邪推があれば、当然ひな薔薇から色は消え失せる。
ひな薔薇の髪の毛が逆立ち、瞳が揺れた。ひな薔薇は後ずさりながら、天井を見上げる。
「誰?」
水緑はすばやく隠れながら、邪気を送り続ける。ひな薔薇の躰が空中に飛ばされ、洋服が裂ける。彼女はくるりと回転して、床に着地する。
灰色の光は糸のように細くなり、ひな薔薇の足首に絡みつき、ゆっくりと締まっていく。天井の影に潜む水緑は、ただ視線だけで彼女を絡め取る。
「ほら。指に止まって」
ひな薔薇は不自由な躰で、天に向かって指先を差し出した。灰色の光は、いっせいに彼女の指先に寄り添った。
光は細い輪を描きながら、まるで遊ぶようにくるくると回る。ひな薔薇の頬がバラ色に染まった。光は彼女に溶けて、やがて暗色は跡形もなく消えた。
「ふうん」
光を操るって、どういうこと? あり得ない! 水緑は唇を突き出した。
その瞬間、奥の扉が静かに開き、空気が甘く震えた。
♢♢♢♢♢♢
すぐに美しいドレスを纏った花音が現れた。
「ひな薔薇、来たのね!」
睫毛の先にダイアモンド、
蜜が滴る赤い唇、
波打つロングヘアは華やかに膨らみ、
リボンが蝶のように揺れている。
「リバティハウスへようこそ」
「花音の声。花音? 綺麗!」
「そうよ。わたくしよ」
「花音! 人の姿の花音!」
ひな薔薇は花音の胸に顔をうずめた。クマの花音は蝦夷の森を束ねる、森の女王だ。冬の森で家族を亡くしたばかりのひな薔薇と出会い、彼女をリバティハウスに導いたのだ。
「おばあさまとゆっくりお別れができたみたいね」
ひな薔薇はこくりと頷いた。
「花でいっぱいの初夏の庭に、おばあさまのお墓をこしらえたの。もう森に心残りはない」
花音は深く頷きながら、ひな薔薇を抱きしめた。
花音はひな薔薇を連れて、ティールームやキッチン、ダイニングルームを案内した。
その一つ一つが古くて懐かしく、それでいて手入れが行き届いている。過去からずっと、そして今でも大切に扱われている証拠だ。
「それにしてもひな薔薇、そのお洋服はどうしたのかしら?」
ひな薔薇のところどころ引き裂かれた洋服を見つめながら、花音は言った。
「多分だけど、歓迎されているんだと思う」
ひな薔薇はそう言って笑った。
でも、笑みの奥で、好奇心に満ちた瞳が揺れている。
普通なら怯える。でも、不思議と拒む色は見えない。むしろ、面白がっている表情だ。
水緑の仕業ね、と花音は呟く。
「私の躰はどんな光でも吸収する。洋服は縫い直すから、平気だよ」
ひな薔薇は、瞳をくるくると動かしながらそう言った。
「あなたの裁縫はおばあさま譲りだものね」
「うん。ぜんぶ、おばあさまが教えてくれた」
あの子、普通じゃない。
人がリバティハウスに棲むなんて。ここでは花音が決めたことは絶対だ。
しかし水緑はおもしろくなかった。
でも、ひな薔薇には妙な引力があるーーそんな予感が、水緑の胸をかすめた。






