ひな薔薇綺譚の
物語
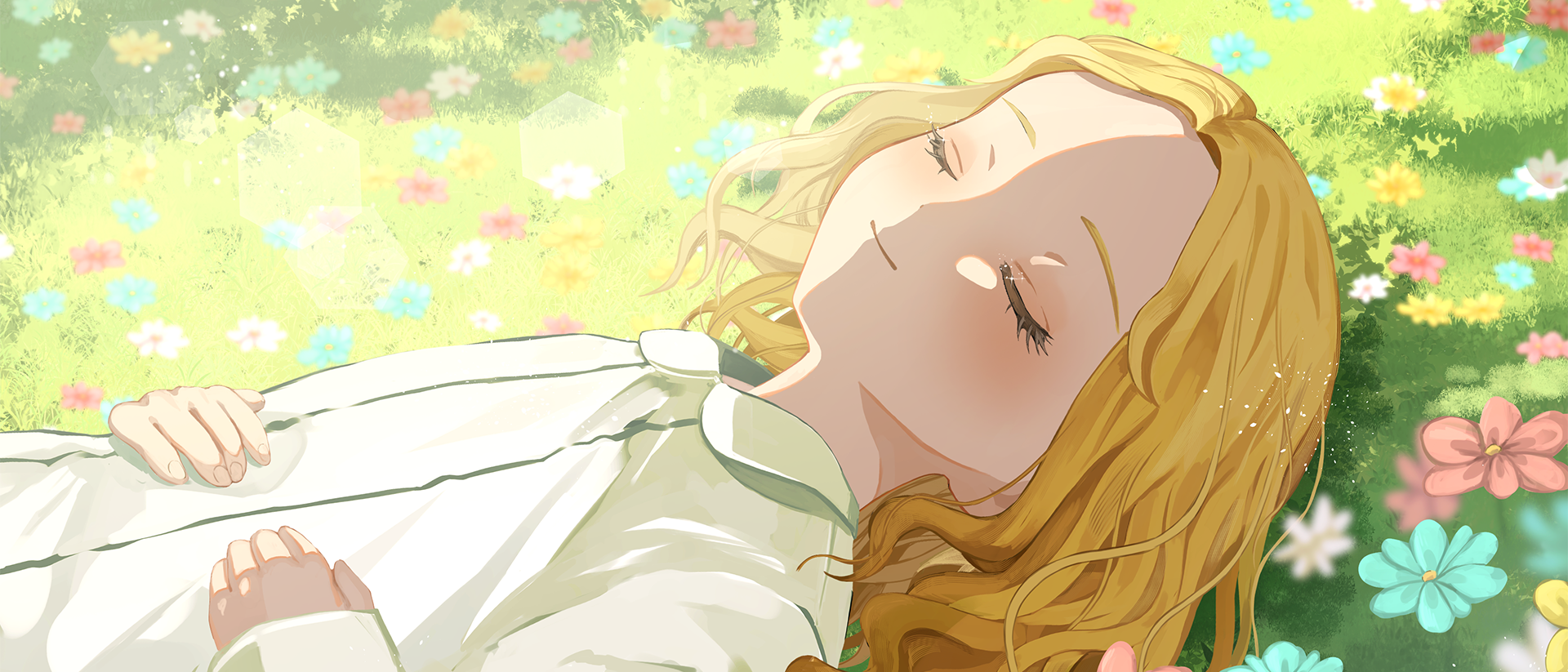
PROLOGUEプロローグ
- 気が付くと私はクマに抱かれていました。
- 温かいと思っていたのは、
- 彼女の毛皮のせいだったのです。
- 大きな躰と漆黒の瞳、
- 金色の太陽のように微笑みながら、
- 彼女は言いました。
- いっしょに暮らしましょう。
- 彼女はあまいハチミツの匂い、
- 私を待っていてくれる
- お日様みたいな
- たったひとつの大きな手。
- 目覚めた花みたいにほほえみながら、
- 心の魔法はまだはじまったばかりです。

第一章
リバティハウス * 札幌 *
第3話奇跡のドレス

「ようこそ、ひな薔薇。キタキツネの水緑、参上」
シャンと音を立てて床に降りると、水緑は両腕を広げた。ひな薔薇は水緑の手中に陥った。
ひな薔薇は軽い。穴の開いたバームクーヘンみたいに重さがなかった。
水緑はおいしいお菓子を愛でるようにそっと、ひな薔薇をベッドに横たえた。ひな薔薇はぐったりして水緑を見ている。とろんとした瞳が水緑を見てつぶやく。
「かわいい……」
水緑は全身から、溢れんばかりの輝きを放った。
瞳から銀色の光、
黒のドレスは肩にかけてたっぷりのレースが施され、
胸元にエメラルドが輝いている。
永遠の漆黒を纏う風化した星が
光と翳の狭間で踊っている。
私は誰よりもかわいいに決まっている。ごらん、私の睫毛の先を。
「まさに」
水緑はおおらかに答えた。
「ひな薔薇、倒れなかっただけましよ。褒めてあげる」
水緑は口元をゆるめながらも、心のうちでひな薔薇の得体の知れない力を恐れた。
あれだけの術をかけても、完全には崩れ落ちなかった――
「……あなたの唇、さくらんぼみたい」
「リップは綺緑堂の新作055番。フルーツみたいな唇が、すぐに手に入るの。あなたにプレゼントしてもいいわ」
ひな薔薇は黙って首を横に振った。唇が微かに動く。……あなたが持っていて。
「ここではちゃんと自分を主張しないと生きていけない。たとえば、お腹が空いたら牙を剥いてみせるとかね」
「…き…ば」
「ほら。これよ」
水緑はそう言って牙を剥いて見せた。ひな薔薇は少しだけ目を見開いたように見えたけれど、ほんの一瞬だった。
「……すごく眠いの」
ひな薔薇は言った。ひな薔薇にはもうひとつ大切な術を施している。しかもすでに成功は目に見えているのだから、眠るにはまだ早い。
眠っちゃだめ、と伝えようとしたとき、花音の腕が水緑を止めた。
「水緑、下がりなさい」
「はい。花音」
花音の腕が飛び出したとなれば、吹き飛ばされないうちに水緑は下がるしかなかった。
窓際のカーテンがかすかに揺れた。ユキウサギの空雪だ。恥ずかしそうに耳を伏せ、ひょっこりと顔を出して、じっとひな薔薇を見つめている。
水緑がちらりと目を向けると、空雪は目をぱちくりさせて、すぐに体を隠すようにうずくまった。水緑はくすっと笑った。小さなかわいらしい見守り手がそこにいることが、いとしかった。
「ひな薔薇、お洋服はお気に召して?」
花音の言葉にひな薔薇は静かに起き上がった。ひな薔薇は美しいドレスをまとっていた。水緑秘伝、身代わりの術。
「私、夢みてる?」
「夢じゃないわ。ほら。鏡の前でごらんなさい」
花音が差し出す手に導かれて、ひな薔薇は部屋の片隅にある鏡の前に立った。水色のドレスは、ひな薔薇のためにあつらえた、ひな薔薇のための洋服だ。
ケープの襟にレースが施され、
程よく膨らんだ袖は翼みたい。
裾は控えめのフリルに
かわいい白薔薇が咲いている。
慎み深いけれど華やかな洋服に、
小さな夢が広がっている。
「嘘みたい。衿ぐりも脇もウエストもぜんぶ、あつらえたみたいにぴったり。こんなに綺麗なドレス、見たことがない」
ひな薔薇はうっとりとそう言った後で、辺りを見回した。
「私が着ていた洋服はどこ?」
「あなたの大切なお洋服はワードローブにしまってあるわ」
花音はクローゼットを開けながら言った。ボロボロになった木綿のワンピースがそこにあって、花音はそれを柔らかなシルクのカバーで覆った。
「シンプルな洋服も美麗な洋服も、どちらも美しいものに違いないわ。すなわちあなたは何も失ったりしない」
「私の洋服はすべておばあさまの形見。とても大切なものなの」
ひな薔薇はハンガーからワンピースを外すと、それを抱きしめた。
「ひな薔薇。これから先、あなたの心を癒すのは古い洋服とは限らない。あなたは縫う人。あなたの静かな愛情が必要な人たちがいる。あなたには新しい洋服が必要よ」
ひな薔薇は花音を見上げた。でも、それはほんの短い時間だった。ひな薔薇は花音に寄り掛かった。花音のドレスにひな薔薇の躰がのめり込むと、大きな腕が彼女を包み込んだ。
花音が静かに躰を揺らしはじめると、たちまちひな薔薇は眠りに落ちた。
その寝顔を見つめる水緑の胸に、特別な感情が広がった。
術を成功させた達成感と、守りたいという思いが混じり合う。
「ひな薔薇、あなたはすでに私たちの仲間よ」
水緑は低く、でも確かな声で呟いた。
瞬く瞳が、ひな薔薇を優しく見守った。







