ひな薔薇綺譚の
物語
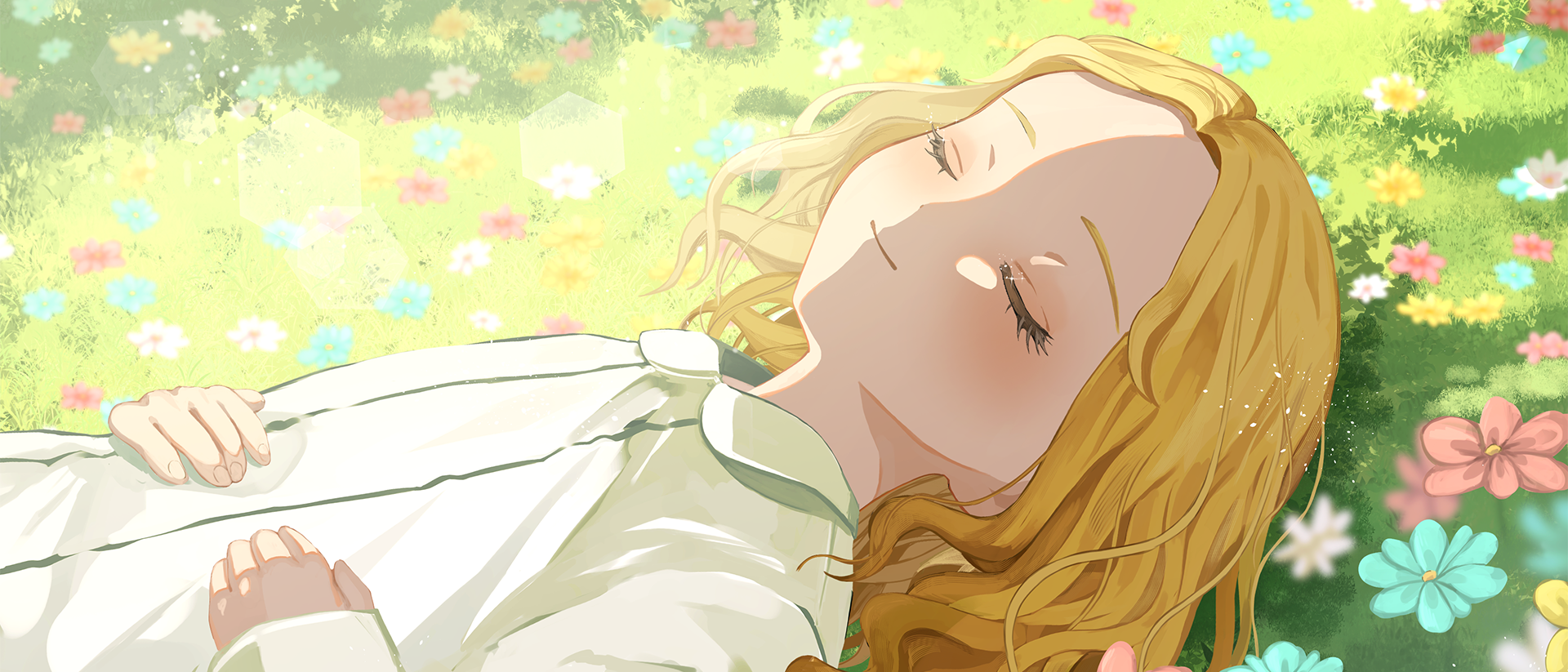
PROLOGUEプロローグ
- 気が付くと私はクマに抱かれていました。
- 温かいと思っていたのは、
- 彼女の毛皮のせいだったのです。
- 大きな躰と漆黒の瞳、
- 金色の太陽のように微笑みながら、
- 彼女は言いました。
- いっしょに暮らしましょう。
- 彼女はあまいハチミツの匂い、
- 私を待っていてくれる
- お日様みたいな
- たったひとつの大きな手。
- 目覚めた花みたいにほほえみながら、
- 心の魔法はまだはじまったばかりです。

第一章
リバティハウス * 札幌 *
第4話森の女王

水緑の魔法術によって、ひな薔薇は深く眠っていた。やがて呼吸が波のように穏やかになり、光と影の揺らめきが夢と現実の境を溶かした。
ひな薔薇は、花音と出会った冬の夜の夢を見ていた。
雪に閉ざされた森に、ひな薔薇はひとり立っていた。
♢♢♢♢♢♢
雪が止み、月明かりがぼんやりと森を照らしていた。
ひな薔薇の長い影が新雪の上に映る。
夜の森で、遠くの家の灯がひときわ明るく見える。
彼女は光に吸い寄せられるように、雪を踏みしめて歩いた。
ようやくたどり着いた楕円形の家は、不思議な形をしていた。
屋根は雪の帽子をかぶり、まるい扉のそばにオレンジ色の灯がともっている。
扉をそっと開けると、暖炉の炎が揺れる部屋に、湯気の立った二つの紅茶が置かれていた。
ひな薔薇はテーブルに腰掛け、紅茶を一口飲んだ。温かさが躰中にじんわりと染み渡っていく。
ぱちんと暖炉の薪がはぜ、ひな薔薇の影が壁に揺れる。
「私、生きてる」
ひな薔薇は呟いた。おばあさまの亡霊といっしょに暮していたけれど、もう我慢できなかった。
ひとりぼっちで家を飛び出して、雪になることを望んでいた。
暖かな部屋でスープを飲んで眠るより、冷たい雪の中で凍える方がいい。
雪になって、誰かに降りつもりたかった。
でも、今、こんなにも温かいことがうれしい。
それでもなお、少し前の危うい自分を思い出して、ひな薔薇はじっと動かなくなった。
♢♢♢♢♢♢
「ようこそ、雪の森へ」
いつのまにか、テーブルの向かいの椅子に大きなクマが座っていた。
ひな薔薇はこの森ではじめてクマに出会った。つやつやとした茶色い毛並みは美しく、その瞳は黒々として可愛らしい。でもクマが歯を剥き出して笑うと、ひな薔薇は一瞬息をのんだ。
「私、勝手にお茶を飲んでしまったの」
「いいのよ。あなたのためのお茶だもの」
「ありがとう」
「どうしたしまして。ひな薔薇」
「……私の名前を知っているの?」
「わたくしは森の女王、花音。森から永遠の命を与えられた者。森の住人のことなら、何でも知っている」
「何でも?」
花音は頷いた。
「ひとつ、訊いていい?」
「何かしら?」
「あなたって女の子なの?」
優雅に微笑みながら、花音はゆっくりと頷いた。
♢♢♢♢♢♢
はらぺこのひな薔薇に花音が準備してくれた食事は、皿に乗った二つの目玉焼きにハチミツを垂らしたものだった。
金色のハチミツをそっとフォークにしのばせて、ひな薔薇はそれを舐めてみる。とても陽気な味がする。たまごは懐かしい味がした。
「お菓子みたいな味がする」
「クマの家の定番よ」
花音は優雅に笑った。
「ひな菊のことは残念だったわ。でも、あの子の寿命よ」
ひな薔薇は目を伏せて、フォークを皿の上に置いた。
「おばあさまのこと、知ってるの?」
「ずっと昔からね」
花音はコポコポと音をたてて、二杯目の紅茶を注いだ。
炎の揺らめきがふっと弱まり、部屋に深い静けさが満ちていく。花音の真っ黒な瞳が、ひな薔薇を射抜くように見つめた。
「ひな薔薇。もう森にひとりで留まるべきじゃないわ。わたくしとともに、リバティハウスで生きなさい」
花音は静かに決意を告げた。
「街の邸でわたくしといっしょに暮らす。そこには仲間がいて、あなたは必然的にみんなといっしょに暮らすことになる。皆、動物であり人でもある。わたくしがそれを可能にしている」
「そこではみんな、どんな暮らしをしているの?」
「リバティハウスでは、みんなそれぞれの役割で洋服をこしらえている。わたくしは洋服デザイナー。思考、容姿、仕草、象徴する心の太陽や雨。お客さまの成りたちのすべてを把握し、心を尽くして、みんなで最高の一着を作り上げるのよ」
「……想像もつかない」
「ええ。まさに想像もつかない美しさよ」
花音の言葉が旋律となり、頭の中で音楽のように鳴り響いた。
それはひな薔薇にとってまったく新しい響きで、いつまでもその音に溺れていたいと願った。
バラ色の頬。微笑みとも泣き顔ともつかない表情。
ひな薔薇は心底驚いたのだ。
未知の世界への期待と、戻れないかもしれない不安が交差する。
ひな薔薇は唇を噛みしめながら、光の方へ引き寄せられるように花音を見上げた。
「私、リバティハウスに行きたい」
ひな薔薇は言った。当然ね、とでも言いたげに花音は微笑んだ。
「ひな薔薇、今夜はここでいっしょに眠りましょう。かなしみは、わたくしの胸で癒すといい」
「あなたと眠りたい」
ひな薔薇がそう答えると、花音は床にごろりと横になった。
ひな薔薇は花音の腕の中に潜り込んだ。
花音は静かに躰を揺らした。
花音のゆりかごに揺られて、ひな薔薇は気が遠くなっていく。
ぱちぱちと薪がはぜる音。花音の息遣い。
いまだ紅茶の残り香が漂う部屋で、ひな薔薇は静かに眠りについた。







