ひな薔薇綺譚の
物語
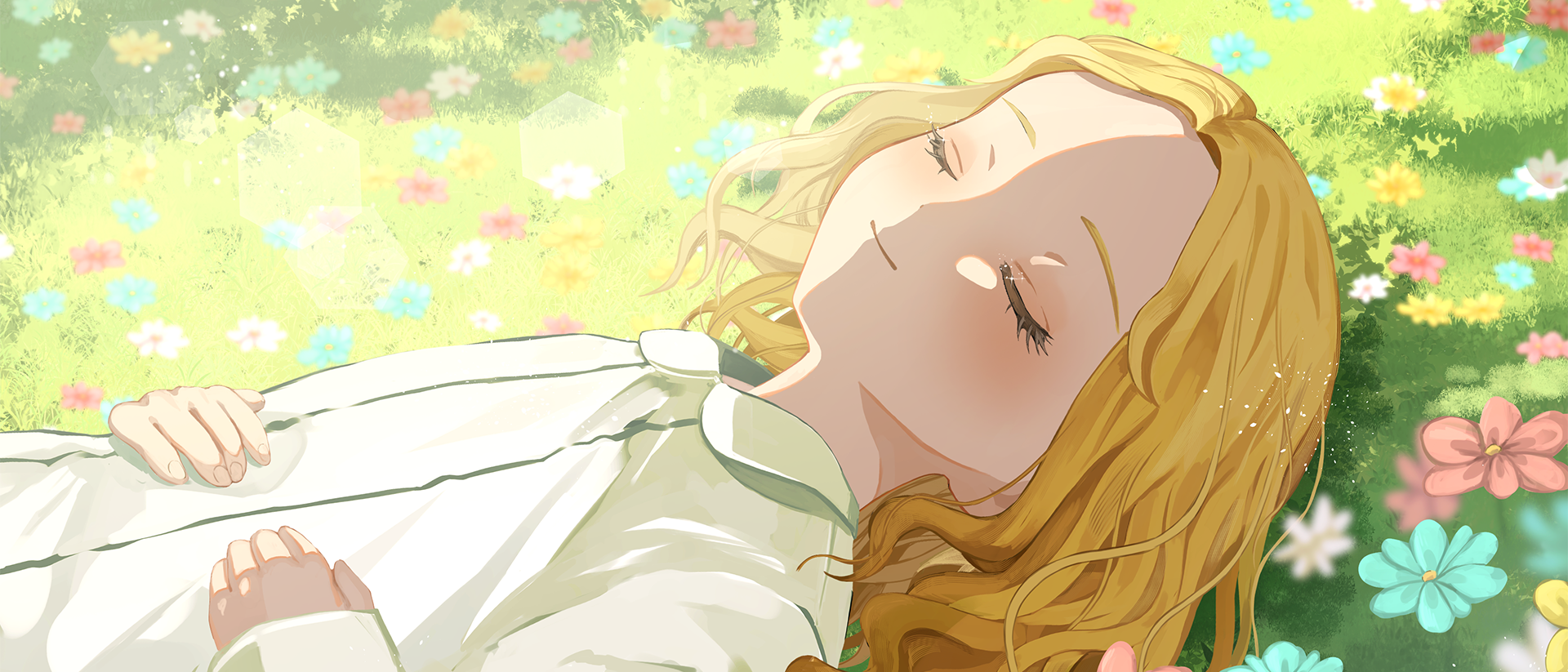
PROLOGUEプロローグ
- 気が付くと私はクマに抱かれていました。
- 温かいと思っていたのは、
- 彼女の毛皮のせいだったのです。
- 大きな躰と漆黒の瞳、
- 金色の太陽のように微笑みながら、
- 彼女は言いました。
- いっしょに暮らしましょう。
- 彼女はあまいハチミツの匂い、
- 私を待っていてくれる
- お日様みたいな
- たったひとつの大きな手。
- 目覚めた花みたいにほほえみながら、
- 心の魔法はまだはじまったばかりです。

第一章
リバティハウス * 札幌 *
第5話アフタヌーンティー

ひな薔薇は朝起きると、真っ先にクローゼットを開けた。
破れたワンピースを取り出すと、そっと手に取り、丁寧に繕いはじめる。
夕べはよく眠れた。
冬の森の夢を見ていたからだろうか。
今、とても気分がいい。
布の端をまっすぐに揃え、糸を通すたびに、昨日の夢が鮮やかに蘇る。
雪に包まれた森、クマの花音、そして――今、リバティハウスにいる自分。
ワンピースがすっかり元通りになると、ひな薔薇は微笑んだ。
きっと大丈夫。そんな小さな喜びが胸に広がった。
♢♢♢♢♢♢
ひな薔薇がリビングルームに足を踏み入れると、柔らかな光が迎えてくれた。
「ひな薔薇さま、おはようございます」
優雅な声に振り返ると、ヒツジの執事メイが立っていた。
淡い光に満ちたその瞳は、執事というよりも、この邸の守護者のように感じられる。
「皆さま、まだお休みでして……ですが朝食のご用意は整っております」
「……おなか、ぺこぺこなの」
「たくさんのおむすびを準備していますよ。お味噌汁とサラダもどうぞ」
ひな薔薇は湯気の立つ味噌汁を口に含んだ。
じゃがいもがほろりと崩れ、玉ねぎの甘みが広がる。
おむすびを頬張ると、じんわりとおなかが満たされていく。
「ん-、おいしい」
「ありがとうございます。台所の者も喜びましょう」
メイは微笑みながら、お茶のポットに手を添えた。
「さて、ひな薔薇さま。本日の午後、あなたを歓迎するアフタヌーンティーパーティーを催します。リバティハウスの住人が皆そろい、あなたにご挨拶をいたしますよ」
ひな薔薇は箸を止め、目を瞬かせた。
「……パーティー?」
「はい。ただし、この邸の者は、皆それぞれに“特別”でございます。あなたにとって、驚きとなることもあるでしょう」
メイは暖かなお茶を差し出しながら、そう言った。
♢♢♢♢♢♢
ひな薔薇を歓迎するアフタヌーンティーパーティーは、薔薇の咲く庭で開かれた。
最初の一杯はジヴェルニアアートのカップ&ソーサーにアールグレーが定番。
ベルガモットのフレーバーに薔薇たちは目覚め、ふくよかな香気が満ちていく。
苺のマカロン、薔薇色のムース、ハーブのスコーン、そして蟹のサンドイッチ。テーブルの真ん中に2メートルを超えるいちごケーキがそびえ立っている。
「ひな薔薇、いちごケーキは私からのプレゼント。ぜんぶ食べてね」
水緑の言葉に、ひな薔薇はケーキを見上げた。
中央にそびえ立つ、ありえないほど大きないちごの塔。
「ひな薔薇、遠慮せずに食べなさい。甘い祝福を味わってちょうだい」
花音の言葉にうなずいて、ひな薔薇はケーキをひとくち頬張った。
ふっと瞳が見開かれ、思わず頬がゆるむ。
「ふわふわ!」
いちごとクリーム、それから蜜の含んだスポンジケーキ。ひな薔薇は食欲旺盛、もぐもぐと平らげていく。
メイは深々とうなずいた。
「リバティハウスのパティシエが作るいちごケーキは、おいしいに決まっている代物でございます。しかしながら、水緑さまの術に惑うことなく完食も間近! 見事でございます」
「ふふ。水緑、あなたの負けね」
花音の言葉に、水緑はマカロンを頬張りながらウインクした。
「メイ、空雪は?」
「花音さま。本日は、お姿を拝見しておりません」
「だったら呼ばなくちゃ」
♢♢♢♢♢♢
花音が水緑に目配せすると、空雪のためのささやかな宴の準備が整った。
花音はひな薔薇に告げる。
「ひな薔薇。歌に合わせてリズムを刻むの。手拍子で、足踏みで、心臓のビートで。空雪を呼ぶのよ」
花音と水緑が美しいハーモニーを奏ではじめた。
ひな薔薇は、歌に合わせて手拍子をしながら、足踏みする。
拍動は土に染み渡り、花々を震わせ、やがて小さな光の粒になって空へと舞い上がった。
歌声は青い空に白い輪を描いて、そこから柔らかな光が降り注いだ。
光の中からシマエナガのユキが姿を見せて、白と透明のあわいを行き来しながら鳴きはじめる。
ユキがひな薔薇の肩に止まったかと思うと、空雪が飛び跳ねながらやってきた。
「あなたが空雪?」
ひな薔薇の言葉に空雪は涙を浮かべた。メイがすかさず、フォローする。
「ひな薔薇さま、ご心配にはおよびません。はじめて会うお相手に、涙であいさつをされるのが空雪さまでございます。動物は泣かぬと申しますが、空雪さま——あるいはウサギ——には当てはまらぬようで」
「かわいい子」
ひな薔薇はユキを人差し指に乗せて、空雪の指先にそっと乗せる。空雪は瞳を瞬かせた。
「ひな薔薇、ウサギの巣に気を付けて!」
水緑が叫んだ。その声に驚いたように、ユキは飛び立ってしまった。
「足元を見て。空雪は気に入った相手を、自分の巣へ招こうとするの。でも、そこは狭くて、空雪以外の誰も生きられないの」
小さな水たまりのような穴が、二人の足元にぽっかり開きはじめている。
地面が吸い込まれるように沈み、庭の薔薇の影が引き寄せられていく。
「やめなさい、空雪!」
花音が命じた。
空雪は涙に濡れたまま、ひな薔薇を見つめて首を振った。
「だって、いっしょにいたいの。あたしの場所で」
ひな薔薇はおばあさまを失った冬の日を思い出した。
ひとりぼっちで家を飛び出して——そして花音に救ってもらった。
ひな薔薇はしゃがみ込んで、空雪を見つめながら言った。
「あなたの巣に連れていって」
ひな薔薇は空雪の涙を指先で拭った。
♢♢♢♢♢♢
空雪の巣は真っ暗だった。
ひな薔薇はすぐに、光の薔薇園を思い出してせつなくなった。
冷たい土の匂いが、肺の奥まで入り込んでくる。
「ここが、あたしの巣」
空雪は誇らしげに言った。
けれどひな薔薇にとってこの巣は、ぴったりとはいかなかった。
指先が冷たくなり、手足は勝手にあちこちを向き、糸の切れた人形みたいに散らばった。
「ねえ、ひな薔薇。もう見えるはず」
空雪はそう言いながら、ひな薔薇の頬を両手で包んだ。
暗闇に目がなれてくると、巣一面にビーズや星のかけらが、鈍く瞬いているのが見える。
「空雪。あなたが集めたの?」
「そうなの。あたし、宝物を見てもらいたかったの」
思い出した。ここは危険な場所じゃなくて、空雪の孤独が形になったもの。
ひな薔薇はぎゅっと集中して腕を伸ばし、ぎこちなく空雪を抱きしめた。
「綺麗だね。あなたも、あなたの宝物も大好き」
だけど—— このまま消えてしまうのかも。さよなら、空雪。
ひな薔薇は目を閉じ、ほんのひととき空雪に寄りかかった。
「……いやよ、ひな薔薇。目を開けて」
目を開けると、空雪の耳がぴんと立っている。
ひな薔薇が小さく息をつくと、空雪は両手を広げた。
散らばる小さな宝物がぱらぱらと震え、まぶしい光を放ちはじめる。
「ひな薔薇、ありがと。
いなくなったら絶対いやだよ。
さあ、外へ行こう。
宝物があかりになってくれる!」
空雪がひな薔薇の手を取ると、巣全体がやわらかく震えた。
二人の足元に光が滲んだ。
♢
ひな薔薇と空雪は光に包まれながら、再び庭に立っていた。
薔薇の香りと青空が、胸いっぱいに広がっていく。
止まりかけていた鼓動が、ようやく軽やかに動きはじめた。
「ひな薔薇、奇跡の生還ね!」
水緑が声を上げた。
「生きてる…私」
朝に感じた「きっと大丈夫」。
あのときは、小さな安心だった。
でも、今は違う。胸の奥から、本当にそう思える。
——私、生きていける。
「やはり——花音さまはすべて見通されていたのですね」
「メイ。ひな薔薇なら果たせる。種を超えて、わたくしたちとともに」
花音の言葉に、メイは頷いた。
「メイ。ミルクティーの準備をしてちょうだい。マグでたっぷりと!」
「かしこまりました。香り深いタイティーをご用意いたします」
花音は楽しげに手拍子する。
水緑は昼間だというのに花火を打ち上げはじめた。
メイは得意のバイオリンを奏で、その旋律はひな薔薇にそっと語りかけるように響き渡った。
ひな薔薇さま。
どうかこのリバティハウスで、すこやかにお過ごしになられますように。
魔境であり、物の怪の巣窟である、この場所で。
あなたの居場所が、静かに守られますように——






