ひな薔薇綺譚の
物語
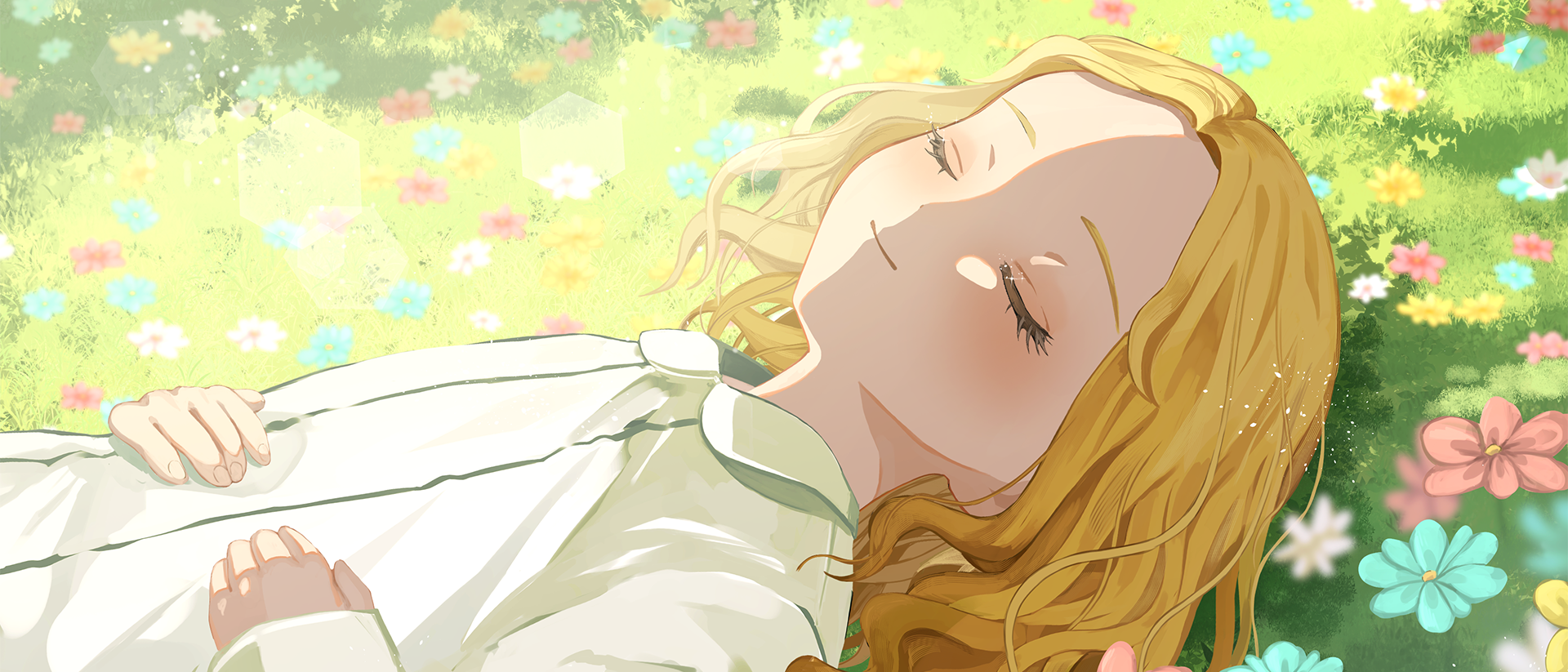
PROLOGUEプロローグ
- 気が付くと私はクマに抱かれていました。
- 温かいと思っていたのは、
- 彼女の毛皮のせいだったのです。
- 大きな躰と漆黒の瞳、
- 金色の太陽のように微笑みながら、
- 彼女は言いました。
- いっしょに暮らしましょう。
- 彼女はあまいハチミツの匂い、
- 私を待っていてくれる
- お日様みたいな
- たったひとつの大きな手。
- 目覚めた花みたいにほほえみながら、
- 心の魔法はまだはじまったばかりです。

第一章
ひな薔薇
第6話旅立ち
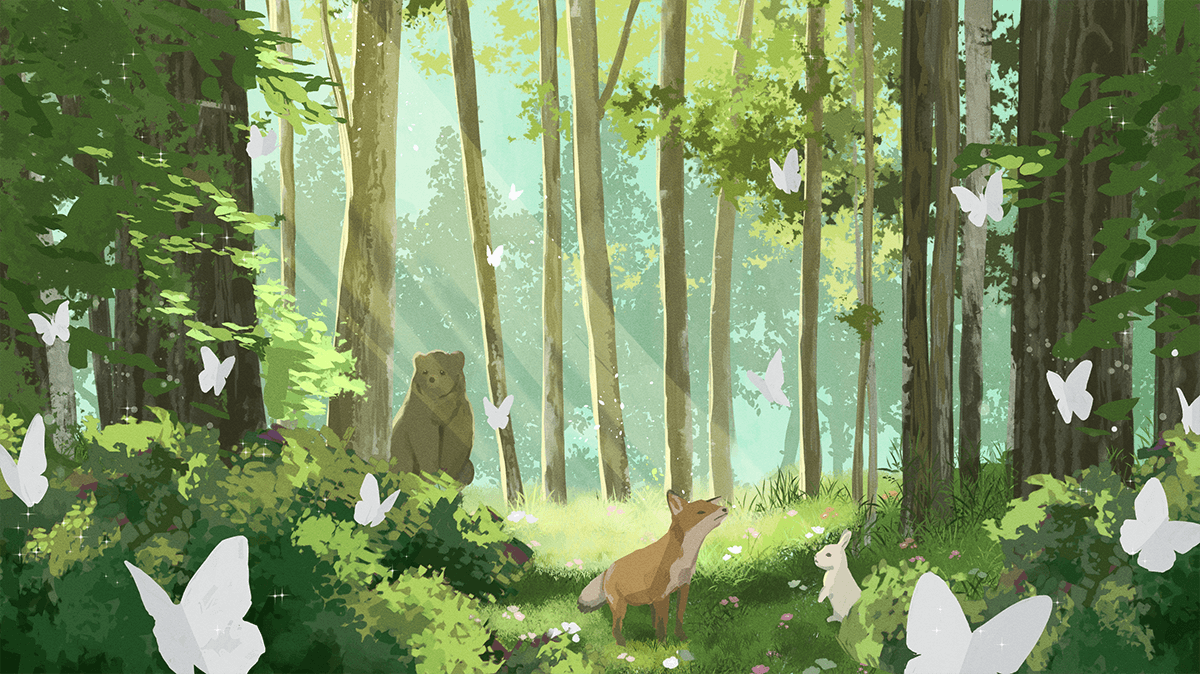
ひな薔薇は花音との再会を約束し、冬の家へ戻った。ひな薔薇には願いがあった。初夏になってたくさんの花が咲いたら、庭におばあさまの骨を埋葬したい。それまで、おばあさまともこの家とも、ゆっくりお別れをしたい。ひな薔薇は思う。いろんなことがゆっくり終わっていくといい。そしていろんなことがゆっくりはじまるといい。
冬の間ひな薔薇は、お得意さまから注文を受けた春の洋服を仕上げていった。裁縫の時間はひな薔薇のなぐさめになった。ひな薔薇にとってそれはいとしい時間で、おばあさまに教わったこの仕事が自分に似合っているとも思っていて、そしてとても好きだった。
洋服は順調に仕上がっていく。ひな薔薇は出来上がった順にそれをハンガーに掛け、部屋に飾った。六着の色とりどりの洋服がすっかり出来上がると、ひな薔薇の胸は高鳴った。
丁寧に作り上げた大切な洋服たち。ひな薔薇は洋服に囲まれながら、未来の持ち主それぞれに手紙を書いた。
もうすぐ森の家を引っ越すこと、洋服の注文はもう受けられなくなること、それから今までのお礼を手紙に記して洋服と一緒に送った。
何人かのお得意さまからは手紙の返事が届いた。どの手紙にも名残惜しい気持ちと今までのお礼が書かれていて、ひな薔薇は確かに手紙の向こう側の人々の気配を感じた。お客さまがテーブルに向かって手紙を書く姿が、私には見えるみたい。
誰かが誰のことを思って、便箋を用意してペンを取り、文字を書く。目で、指先で、文字を追いながら。少しだけ心を震わせて。書き終えた便箋を綺麗にたたんで封筒にしのばせる。気に入った切手を貼りつけて、ポストに投函する。コトリ、と着地する音がすると、安堵の気持ちでいっぱいになる。やっと手を離れた。これで永遠に忘れてしまってもかまわない。でも、返事が届くととてもうれしい。天にも昇る気持ちになるーー
ひな薔薇は最後の洋服を手にしたお得意さまの気持ちを案じるように、再び返事を書いた。すると再び激励の手紙が届き、ひな薔薇はやっぱり心を込めて返事を書くのだった。そんなやりとりが幾度か繰り返され、それもいつしか終わりを遂げる頃、いよいよ春がやってきた。
春が訪れるとひな薔薇は森の奥へ向かった。春の森では新緑が芽吹き、福寿草が咲き、桜の花びらが光に透けてひらめいている。
ひな薔薇は花の波に目もくれず通りすぎ、真っすぐにミズナラの木であるルビーの元へ向かった。ひな薔薇の覚悟はたった一つだけ。もしもルビーが枯れて倒れていたら、きっと私の手で埋葬したい。ルビーの枝の一葉を胸に仕舞って、おばあさまのそばに埋めよう。でも、もしも生きていたら。私はルビーを見上げて、春の風が冷たくなるまで抱いていたい。
ふと春風が吹いて土埃がひな薔薇の前を舞い、目を閉じた。風が去ってひな薔薇が目を開けると、遠くの方に豊かな葉をつけたルビーを見つけた。
「ルビー!」
ひな薔薇はルビーに駆け寄った。再び強い風が吹いて枝が揺れ、ルビーの葉が静かに発光する。ひな薔薇はルビーを抱きしめた。ひな薔薇の目に森が映った。新緑は優しい黄緑色で、それでいて太陽に向かって逞しく伸びていく途中だし、花々は明るく咲き誇っている。
ひな薔薇はさっきまで考えていたことをきれいに忘れて、心躍らせながらルビーから離れた。ひな薔薇は土に耳をつける。草の上にてんとう虫が這っている。トカゲが目の前を横切っていく。蝶がやってきて、瞼の上に止まった。ルビーの葉陰がひな薔薇の顔に翳りを作る。心臓がどきどきした。
ルビーの元にはシルヴィアが眠っている。もしかするとシルヴィアはとっくに誰かに生まれ変わって、どこかでこの春を迎えているかもしれない。
シルヴィア。ルビー。私の音が聴こえる? 私の中を流れるブルーの血の音。
冷たかった耳の下の土は、温められてぬるくなっていく。ひな薔薇は立ち上がり、ルビーを見上げながら言った。
「ルビー。もっと花でいっぱいの季節になったら、私はこの森を出ていく」
春の森は深まって、すぐに夏が来るだろう。ひな薔薇は夏を待ちわびながら、春の森のひとつの芽になった。
夢の森に初夏が訪れた。ひな薔薇は大きなショベルで、花畑の横に土を掘りはじめた。ひな薔薇は思う。いたずら好きのおばあさまは、きっと人が隠れるくらいの深い穴が好きだから、できるだけ大きな穴を掘りたい。土は意外に柔らかく、思ったよりもさくさくと仕事が進んだ。三十センチも掘ると、とても美しい形の穴が出来上がった。
「おばあさま。綺麗な穴ができた」
穴は美しい卵の形をしていて、ひな薔薇はとても気に入った。ひな薔薇は穴の中におばあさまの遺骨の一つ一つを静かに納めた。
「おばあさま。この卵の中から、またいつか生まれてきてね」
ひな薔薇は幼い頃に針を刺したマーガレットのハンカチを骨の上に広げた。
「おばあさまのいちばん好きなハンカチよ」
土をかぶせ、まるい石を墓石としてあつらえると、おばあさまの安息の地はできあがった。おばあさまが眠るすぐそばには、薔薇やラベンダー、チューリップが咲きほこり、ミツバチが羽を鳴らしてうなっている。小鳥のさえずりが聞こえ、木の上からエゾリスが顔をのぞかせる。
「おばあさまは欲しがりだから、もっと、って言うかもしれないね」
ひな薔薇はそう言って微笑んだ。ひとひらの蝶がやってきて、ひな薔薇の周りをくるくる回った。ひな薔薇が口を開けると、蝶はそこで羽を休めた。ひな薔薇はゆっくり口を閉じた。蝶の羽音が小さな振動になって、鼓膜に響いてくる。暗闇の中の蝶は、びろうどの羽できらきらと瞬く。ひな薔薇が再び口を開けると、蝶はそこから飛び出して薔薇の花に止まった。
「おばあさまの好きな花がたくさん咲いたね。おばあさま、もうさびしくないね。私は今日、家を離れる」
蝶は再び飛びたち、ひな薔薇の右耳に潜り込んだ。ひな薔薇は風の声に耳を澄ませる。
さよなら、森のぜんぶ。さよなら、おばあさま。蝶はひな薔薇の左耳から飛び立つと、名残惜しそうに愛の粉を振り撒く。それから薄紫の光になって、澄んだ空に消えていった。
夢の森にたったひとつ佇む老いた家は、いよいよ果てる準備をはじめる。家は静かに目を閉じる。家と外、二つの世界の境界線が消えてなくなっていく。透きとおった窓辺の幕は黒く燃えて、明るい大気に散っていく。窓は宇宙に昇っていく。
太陽が高いところにあって、今日ははじまったばかりだよと話しかける。ひな薔薇は森の輪郭を後にして街へ向かう。古い思い出がひな薔薇の背中を押し続ける。古い夢はもうどこにもないよと教えてくれる。


